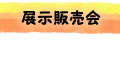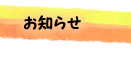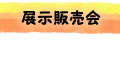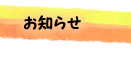ナラヤンプールの小学校から出発前の2月にニュースがあった。3名がマークシート方式のテストに合格し、政府の奨学生となって進学できることになった、というのだ。村の人々があまりにも盛大に歓迎してくれるので、常は連絡なしに出かけていって、普通の村の風景の中に入って行くのだが、今年は連絡を入れてもらうことにした。その子どもたちに会いたい、と思ったからだ。
その他に、今年は妹の小木節子が初めて同行することになり、なにかおみやげを持っていきたい、と言っていたので、あれこれ考えた末に校庭に果物の樹を植えることにした。
こうして夏の始まりかけたダッカへ、今年は2人の旅である。
果物の樹を贈ろう、と思いついた時、私はすぐに村の貧困層に属するサクラ・モヒラ・ショミティの女性たちのことを思い浮かべた。彼女たちに果実の樹の世話をしてもらい、マーケットで果実を売ってその利益の、例えば10%を村の学校のために使う、という案はどうだろうか。「すごい発想!」と有頂天になって現地の世話人ハク氏に相談したら、にべもなく、「子どもたちに食べさせてやれ」と言われてしまった。それもそうか。果樹を植える土地、女性たちをまとめるリーダーのことを考えたら、それが妥当な答えだろう。それに加えて子どもたちもおいしい果物の恩恵に与っていないのだから、これはまさに知ったかぶりの浅はかな発想だったと多いに反省することになった。
果樹はダッカの園芸店で買った。バングラデェシュで生まれ、今や巨大なNGOグループに成長したBRACKが経営するAarong
デパートの系列の園芸店である。田舎に行くのになぜダッカから果樹を買うのか、と疑問に思い訊ねたら、田舎には改良種がなくおいしい果実をつける樹がないということだ。声をかけたら7人が一口1000円で参加することになり、その合計金額にサクラ・モヒラ・トレイディングが補足して12本の果樹、成長するまで牛や山羊に芽を食べられないように保護するためのレンガ、元肥を買った。樹を植えるためのもろもろの労働は村の人たち、そして日々の世話は小学校の先生たちと村の人たち全員。これを村の教育責任者ホッサンさんの前で、ハク氏に英語とベンガル語で書いてもらうことにした。出資した人たちの名前も全員列挙してもらった。これは、村の人たちとの共有性を強調するためと、書く、という習慣を村に導入したかったからだ。ハク氏もこちらの意向を汲んで、何度も繰り返し村人に説明したあとで、おもむろに特製万年筆で書いていた。
買った果樹は、マンゴウ、パパイア、グァヴァ、ソフェダ、レモン、ライチ、ベルフルーツなどである。2本はおまけしてもらった。ところで、初め校庭には7本植えることが可能だとハク氏は言っていた。そして村人は数日前に校庭に7本の穴を掘り元肥を入れて待機していたのだ。余分はついつい大きくなってしまうハク氏の夢の分である。果樹は1本800円前後、7本分の果樹とレンガと元肥は日本からのおみやげとしてけじめをつけ、ハク氏の夢の代金は彼が負担することになった。それらの苗木は彼のおじいさん側の親戚、ホッサンさんが村に提供するモスクの庭に植えて管理してもらうことになった。彼も奥さんも笑って夢の代金を支払った。
今年はサクラ・モヒラ・トレイディングが経費の全額負担をすることができたことから、皆の心にゆとりがあった。今までは現地の経費を負担していたハク氏も、今年は「子どもたちにチョコレートをお土産に持って行こう」と提案した。誰も反対しない。渋い顔もしない。皆、そうしたいのだ。出て行く経費にひやひやしながら村にかかわってきた過去を思えば、ビジネスと結び付けることで、このようなボランティアの活動が本来持ちあわせるべき心のゆとりを取り戻したことは、活動を無理なく継続・発展させる大切な要素ではないだろうか。
村に向かう道路が快適な高速道路になった。昨年はまだ工事中だった道路が完成し、ダッカの渋滞を抜け出た後は順調にすいすいと進むはずだった。ところが、途中で交通事故が発生し、突然巨大な駐車場と化した新品の道路で、ほこりと排気ガスを吸いながらエアコンディションの効かない車中で延々一時間を待たされるはめになった。事故の処理のあまりの遅さに、事故当時者への同情も忘れて、暑さと疲れでいらいらしてきた。隣り合わせたミニバスで、日本人が電話をしていた。「私のスケジュールが……」ひがむわけではないけれど、こちらは運転手を含めて7人、あちらは同じサイズのミニバスに運転手と2人、電話付きで仕事仕様のバスである。悪いことにはコミラという大きな街を過ぎてから、ナラヤンプールに向かう地方の道は崩れ放題で修理もされないので、でこぼこは日ごとに、しかも車が通るたびにアスファルトが崩れて、徐行運転で穴ぼこを避ける努力をしているにもかかわらず、動くたびに頭や肩や顔を車の壁面に打ちつけ、ようやくたどり着いた時には皆、痣と打撲と振動で疲れ果て、元気をしぼりださなければならないありさまだった。8時に出発して昼過ぎには着く予定だったのに、6時間以上を交通に費やし、その間待ちくたびれた子どもたちは帰宅、サクラ・モヒラ・ショミティの女性たちも一旦は集まったものの、解散していた。
帰りは日のあるうちに出発しないと、あのでこぼこ道路は危険である。つまり、村で過ごす時間は2時間くらいしか取れないということ。サクラ・モヒラ・ショミティの女性たちは今回、小さなビジネスを始める時期にあり、是非とも話合いの時間を取る必要があったので、学校で子どもたちと遊ぶどころか、用事を済ませて早々に退散せざるをえなかった。急かせられて、校庭を後にしながらオカリナを、お土産に持ってきたことを思い出した。オカリナを奏し、自ら焼く方に秋から頼んでおいたものである。そそくさと先生に吹き方を教え、好きな人がいつでも吹けるように管理してほしいと頼んできた。吹き方を教えている時、村の若者たちが興味を示し吹きたいと言ったので、ホッサンさんに頼んで子どもたちばかりではなく、村の人たちが好きな時に練習できるようにしてほしい、と3回も繰り返し頼み、ついでにそれもハク氏に書いてもらった。(マッタク、ウルサイ ニホンジン ノ オバチャン ダ)それにつけても、あちこちで皆、音楽を聴くことを楽しみにしていた。ハク家の台所のお手伝いの人たちやパーティーでも、へたな私のオカリナでも催促されて「さくら、さくら」などをよく吹いた。特に新しく来たお料理の女性は6歳の娘連れだったので、遊びながら台所で日本の童謡を吹いた。残念なことに彼女は母親以外の人には決してしゃべらず、目を合わせることもしなかった。 |