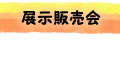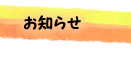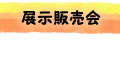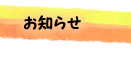高速道路が開通し、でこぼこ道で車が転倒し犠牲者が出た道路が平らになり、嘘のように快適にナラヤンプールの学校に到着。マイクロバスの借り賃がドラマチックに高騰し、運転手はレースに出場している気分でぶっ飛ばし、そのせいかどうか、帰路に決まって立ち寄る途中の町、コミラでのお茶休憩も村の野菜マーケットも素通りした。「礼儀正しい運転手を手配するように」と3メートル先から声を響かせていたハク氏も、もうそのような頓着はしなくなった。便利さの他になにかが着実に変わっている。ともあれ、朝の6時にダッカを出発して10時半には目的地に到着。この時間の短縮は夢のようだ。運転手に挨拶したら、驚いて顔をあげ、それだけだった。問題らしい問題といえば、レンタルの料金が倍額以上になり、クーラーが故障していて、皆、脱水状態に近かったことぐらいである。
誰かが見張っていたのだろうか。バスが学校に近づいた頃、先生と子どもたちが教室から走って出てきた。これがバングラデシュかと疑うほど、皆すばやく整然として校庭に列を作った。
「アッサム・オアライコム!!」と挨拶をするかしないかのうちに、歌が流れ始めた。「We
shall overcome, we shall overcome…♪、♪…」皆、精一杯に口と目を開けて英語で歌っている。力が伝わってくるような歌い方だ。お礼を言おうとするのに、声も胸も詰まってしまい、代わりに涙腺だけが詰まろうとはしなかった。5月に始まったばかりの週1回の音楽のクラス。3ヶ月で彼らは英語の歌詞を5番までと曲を覚えて、歌っている。外は日差しが強いからと皆で教室にすし詰めになったが、そこでも歌ってくれた。「We
shall overcome…」なんの脈絡も無く、このような言葉が私の心に浮かんだ。「いまにみておれ、やったるで!」
子どもたちの写真を見て、すでに気づかれた方もあるだろう。水色の服は制服のようなものである。ナラヤンプール小学校が私立から政府の経営する公立学校に昇格(?)した。金銭にゆとりのある家庭は数種類のデザインの中から自分の気に入った服を選んで買うのだそうだ。感無量。石版もやっと過去のものとなり、子どもたちはノートを使い始めた。
前の晩、私の留守に村の教育担当、ホッサンさんからハク夫人に電話があった。「政府の教師の一人が私的に雇った数学と英語の先生は、公立学校となった今、存在が矛盾しているのではないか、と反対している」というのだ。ハク夫人が付け足して言うには、「ホッサンは日本から金を受け取っている、仲介のハク氏も日本の金を受け取っている、という噂があって、ホッサンさんは責任を取りたくないからやめにしたいと思っているし、私たちも誤解を受けるのは困る」と言うことだ。ハク氏は、「妬み、妬み」と笑って取り合わない。
「公立学校になって何が変わるか。英語と数学の教師がいなくなり、せっかく奨学生を出し続けるまでに育った教育レベルが元に戻るだけだ。」彼はその類のことはいやというほど経験してきている。その根拠は「私的に雇った教師の給料は政府の教師のそれよりも高い」ということだ。だが、彼は、公務員には昇給、年金などが保障されているが私的に雇った教師たちには保障が何もない上時が来たらそれで終わりになってしまう。さらに雇用も創出できている時になにをほざいているのか、と思っているのだ。さらに夫人に問い続けると、「メンテナンス用の寄付は歓迎。音楽の教師は問題ない」ということだ。そして反対しているのは、教師一人だけ。村人も子どもたちも英語や数学の授業の廃止は夢にも思っていないらしい。結局、その夜にまた村から電話があって、すべてが解決したと伝えられた。それでも夫人は気にかけて、政府の学校なのだから、邪魔にならないように学校に立ち寄らないほうがいい、とバスを降りるまでハク氏を説得していた。そして相変わらず彼の答えはこうだ。「行って直接話してみようではないか。」私はといえば、過去5年間、ハク氏に駆り立てられるようにして資金を工面したことに絡む諸々のことを思い出しては、うつうつとしていた。
この一夜の時間は何だったのだろうか。教師たちも子どもたちもそんな話があったことさえ知らないようにいつものとおりだ。ホッサンさんにとりあえず、教師2人分の給料の受取にサインをしてもらった。すべて私が整えて、サインだけという用紙を作ったのだが、実はお金はハク夫人に預けてあって彼はその時には受け取っていないのだ。ま、生きた時間の長さの中ではこのようなこともあるかもしれない。それにこのペースで過去3年間、信頼関係でお金が渡されていたのだ。子どもたちの知らない所で推移した問題と解決の結果、英語と数学の授業は続けられることになりました。
誰が見張っていたのか、帰りの道でもバスが学校にさしかかると、教師も子どもたちも走って出てきて、手を振ってくれた。ナントカバカの類で、「私の子どもたちは英語ができる、私の子どもたちは音楽もわかる、」と気が付けば孫のように自慢気に思っているが、現実にはもう少し気持ちの距離を置いたほうがよいのかもしれない。何年かが過ぎた時、「昔、突然日本人が村にやってきて…」と誰かが思い出すこともあるだろう。
ダッカの家で、ハク氏が「あのようなことはダッカのどの学校でもできない」と、歌を歌ってくれた子どもたちの音楽教育の成果を評価するコメントをした。私が、「村のプロジェクト、基盤がきちんとできてよかったですね」と言ったら、あろうことか、彼は顔中に涙を流した。「あの村の人たちはチャンスを無駄にしなかった。ところが私の生まれ故郷の村はどうだ。同じようにチャンスを与えたのに、私たちは彼らの村に行くことさえも止めてしまった。」
いつも冗談の陰に隠してはいても、彼なりにうつうつとした想いを自分の中に留めてくれていたのだろう。国のためにと、ひたすら突っ走ってきた人生。年を取って病気になってから、想像もしていなかった形で果実を見ることになり、どんなに嬉しかったことだろうか。
「We shall overcome… 今にみておれ、やったるで!」 |