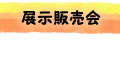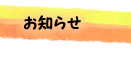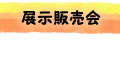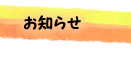8年の時の経過が嘘のようだ。バングラデシュに関った8年は、時がすべるように過ぎたようにも思われるし、矢のごとくに飛んでいったようにも感じられるし、止まっていたかのような錯覚を覚えたりもする。何が変わり、何がそのまま残っているのだろう。
バングラデシュの経済は上々だということだ。隣接国の経済発展が目覚しく、その恩恵に少なからず与っているようだ。ダッカには近代的なビルが次々と建ち、その屋根はお金がたまり次第増築できるように鉄筋を残しておく、というスタイルではなくなった。ユニバーサルなオフィスビルやレストランが建ち、その傍らで、10年前と同じ姿で、労働者たちがほこりの街をアルミのお弁当箱を持って歩いていく。車の窓から通行人を見ながら、「あの人は衣料工場の人」、「お掃除の人」等と元駐日大使だったハク氏が説明をしてくれる。その判断の根拠を問うたら、着ているもので判断できるという答えだった。なるほど、彼も夫人も家を出る時はいつも絹の服に着替えている。それを聞いて以来、たかが買い物だからといって、家庭着でそのままという気楽な態度を反省し、服を改めて出るようになった。
ハク夫人の親戚筋の結婚式に招かれることになった。婚約パーティ(これは欠席)に始まり、花嫁、花婿のそれぞれの家でのターマリック・セレモニーがある。家に入りきらない招待客の数なので、マンションの駐車場や庭を飾り立てて会場にし、客たちは花嫁と花婿が一生美しく幸せであることを祈って、ターマリックを顔や手に塗り、食べ物を口まで運んで食べさせてお祝いとする。ターマリックはカレーの素だ。翌日、翌々日は花嫁、花婿の親がそれぞれ借りた結婚式場で結婚式があった。花嫁さん側の式には、家事の手伝いの人たちも招かれていて、身なりを彼らなりに整えて、隅のテーブルに列席して、楽しそうに心ゆくまでお祝いのピラフを食べていた。翌日には、親しい人たちが立ち会って、お祝い品を開き、花嫁を花婿の家に送り届けて、結婚が成立する。私は合計4日、式に出席したが、お祝いは1回差し上げればいいそうだ。花婿は実業家の家庭の出身でお金持ちなので、彼の家に至る路地、通路、会場となる家の広場はすべて豆電球の花で飾りたて、極楽浄土を再現したかのようだった。プロのエレキバンドも呼んでいた。このバンドがへたでうるさいのに加え、これみよがしに飾り立てたものだから、「洪水で被害にあった人たちが大勢いるのに…」と顰蹙をかったそうだ。花嫁は首が折れそうなほど幾重にも金の飾り物を下げていた。金の重さを量り、価格を計算し、それが花嫁の財産となるそうだ。結婚式場だって、その家の財政状態を示すので、選びに選んで精一杯格の高い場所にしなかれば、「花嫁の親は貧しいので、ミニマムの場所です」などと高級サリーを身に着けたオバサマがたに言われてしまうのだ。花嫁は、花婿がオーストラリアに帰化した銀行マンなので、あこがれの先進国の生活を始めるということだ。
花婿の家は旧東パキスタンの首都であった場所にあり、アラビアンナイトに出てくるような狭い路地や家並み、豆電球の極楽浄土とは対極の、30ワットくらいの裸電球の地元商店街の生活がお伽話の中に入り込んだような印象で頭に焼きついた。パキスタンの話のついでに、車の中で訊ねたら、ハク氏は、インド、パキスタン、バングラデシュと3回、夫人はパキスタン、バングラデシュ、運転手のコビールさんはパキスタン最後の年に生まれほぼ初めからバングラデシュ人という国籍の経歴を生きていた。
ある家の前に女性や子どもたちが30人くらい、集まるでもなく集まっている。なんだろうと思って訊ねたら、その家の主は奇特な人で、食べ物を出すので、それを目当てに時間になると人が集まるそうだ。祝いごとでも、特別な日でもなく、食べ物を提供しているということだ。
今年のモンスーンはダッカだけではなく国中のあちこちを水に埋めてしまったが、洪水の被害に会い、家を追われた人たちは街で物乞いをして生計を立てることもあるようだ。マーケットの広場のあちこちで、女性たちがパンハンドルの手を出していた。新聞には、水の中に投げ入れられる食料のビニール袋を、泳いで掻き集める少年たちや主婦たちの水上に浮かぶ顔の写真が載っていた。夏の海でボール遊びに興じているような光景である。日本だったら、リストを作り、家族数も考慮して、しかるべき場所で手渡すかもしれない。だが善意の人たちが思いついてやってきて、施しをするという現地流では、これが妥当な方法なのだろうか。被災者は暗い事実を述べる暇も惜しんで、われ先にと食べ物を拾い集めていくようだ。衛生状態も悪くなり、死者、病人も出たと報じていた。ハク家でも、手伝いの者を使いに出して、食べ物を現地で配らせ、親戚筋の被災者には、水清浄剤も届けさせていた。
通学路が水で溢れ、休校になるところもあるようだ。道路も雨の影響を受け、あちこちで水溜りの場所がそのまま穴になり、交通状態を悪化させている。道ばたの水溜りには小魚さえも泳いでいる。膝まで水につかりながら、ほうほうの態で母親が子どもを送り迎えするというのも、庶民のこの季節の登校風景らしい。学校ならいざしらず、仕事の場合はどうするのだろう。それが理由かどうか知る由もないが、銀行も郵便局もやたら効率が悪く、長蛇の列が停滞して進むことがない。だからというわけでもなかろうが、今日は、病院に行く日、今日は郵便局の日、銀行の日と決めて、それが一日の仕事のすべて、という印象を受ける。その分、食べる時間、人と交流する時間は豊富にあり、慣れてくると、そのようなスローライフも悪くない、という気持ちになる時もないこともない。
ビーマン・バングラデシュという国営の航空会社が機体の都合がつかず日本との運行を取り止めにしたと#8で報告した。それで今回は待ち時間の少ないシンガポールエアラインを利用することにした。懐には痛手だったが、時間的には便利である。帰路の座席確認のためにダッカ市内のオフィスを訪ねたら、そこは高級感に溢れるビジネスの場所だった。気後れの中で、コンピュターに向かう窓口の男性二人を見たら、肌の色が薄く、癖のない英語を話し、洗練された物腰は、ヨーロッパのエリートを連想させた。その建物のエレベーターには、雇用された身障者が「ボタン係」として配されていて、木製みかん箱で作ったような車椅子から、一心不乱に階数のボタンを押していた。
|